2025.03.04 UP
 精神科医でありながら起業家でもある物部真一郎さん。スタンフォード大学でMBAを取得し、2014年に医療系スタートアップを設立。その後もいくつもの起業を経験し、今なお新たな事業に挑んでいます。“人がどうしたら楽しく生きられるか”を追求し、自分らしく生きる道を切り開いてきた物部さんの軌跡をたどり、その生き方から得られるヒントを探りました。
精神科医でありながら起業家でもある物部真一郎さん。スタンフォード大学でMBAを取得し、2014年に医療系スタートアップを設立。その後もいくつもの起業を経験し、今なお新たな事業に挑んでいます。“人がどうしたら楽しく生きられるか”を追求し、自分らしく生きる道を切り開いてきた物部さんの軌跡をたどり、その生き方から得られるヒントを探りました。
Text&Edit_Kazutaka Yamashita
Photograph_Koichi Chihara
“人の幸せを純粋に願い、
応援できる人になりたかった。”
京都府に生まれ高校時代までを過ごした物部さんは、大学入学を機に高知県に移り住みます。

物部さんが大学時代を過ごした高知県の風景
「高知の大学を選んだのは縁を感じたから。高知には物部川や物部村があるんです。あとは、中学生の時によさこい踊りを体育祭で踊った楽しい記憶もあって。惹かれていきました」
高知医科大学(現・高知大学医学部)に進み精神科医を目指した理由を「人の命を救うことも大切だけれど、楽しく生きることの手助けをしたかった。精神科医ならばできると考えた」と話す物部さんですが、高知県の人びととの出会いがその後の生き方を変える大きな転機になったといいます。
「高知で出会った人たちが本当に良かったんです。誰かの成功をまるで自分のことのように喜ぶ人たち。他人と比較して勝ち負けを感じることが普通だったそれまでの価値観から、人の味方になりたい、心から応援できる人になりたい、みんなで楽しみたいと思うようになりました。それまでの人生では想像もできなかった価値観の変化でした」
“憧れていた雑誌の創刊。小さな成功体験に。”
物部さんが初めて起業に挑戦したのは大学2年生のとき。2003年当時、関西で人気のあったカルチャー誌『L magazine』に憧れていた物部さんは、高知ローカルの若者向けタウン誌をつくろうと思い立ち、仲間とともに手探りで創刊にこぎつけます。
「インターネットが普及し始めたころで、まだ情報が少なかったこともあってタウン誌への反応は良く、最大3万部まで成長しました。街の人から直接反応を聞けたり、インタビューをしたりして関係性が深まって、高知が自分の街だと感じられるようになりました。読者や取材協力者から感謝され、高知に恩返しもできる。楽しかったし、起業って素晴らしいと心底感じました」

エリア限定とはいえ社会にインパクトを与えた実感があり、小さな成功体験としてその後の起業を支えるものになったと振り返ります。加えて、仲間とともに目的を達成することの楽しさが深く刻まれることになりました。
“半径3キロの深さか、80万人への広がりか。”
卒業後、精神科医として奈良県と三重県の病院で充実した日々を送る中で、東日本大震災が発生。医師として派遣されますが、当時研修医だったこともあって十分な貢献ができなかったと話します。医療現場で感じる課題とより広い社会貢献への願い。その思いは日に日に強くなっていきました。
「このまま精神科医を続ければ半径3キロ圏内の患者さんには深い貢献ができる。一方で、学生時代の起業では、影響の度合いは薄くとも多くの高知の人びとに貢献できていた。深く、より広い貢献をするためには、専門である医療分野で課題解決するような起業をするのがいいんじゃないか」
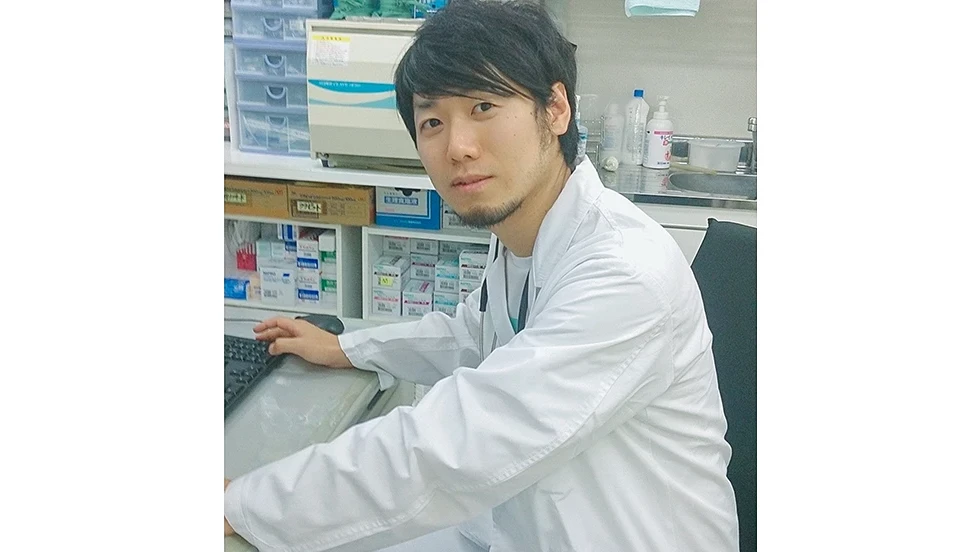
研修医を経て、病院で精神科医として勤務している様子
この思いがMBA留学への挑戦につながります。医療現場での課題は認識したもののどのような形で解決すればよいかを学び、考える時間が欲しかったという物部さん。夢を実現するHOWを手に入れるために海外のビジネススクールで学ぶことを決意します。1年間の猛勉強のすえ、第一志望であったスタンフォード大学留学を現実のものとし、世界中から集まる優秀な人びとと出会うことに。物部さんの価値観を変える2度目の転機が訪れます。
“3か月で分かった、人は皆同じ人間だということ。”
スタンフォード大学のMBAプログラムは実践的で素晴らしい授業が用意されていたといいます。
「授業で一番良かったのが、Googleの元CEOだったエリック・シュミットが講義してくれた授業。20回のうち10回以上エリック・シュミット自身が教壇に立ちました。チームを組んで起業プランを考え最終日に発表するんですけど、ベンチャーの神様のような人が自分たちのアイデアにフィードバックくれるというのは最も大きな学びと経験でした」
学生たちも、世界中から選りすぐりの人材が集まっていました。とんでもなく優秀だと感じる人たちの中で過ごすうちに、物部さんはあることに気づくことに。
「自分よりも1兆倍くらい頭が良くて、何を言っても自分よりも1兆倍前に進んだ考え方をするような、すごい同級生がいたんです。始めは喋るのが怖いという気持ちがありました。スタンフォードでは寮生活だったので、部屋での飲みの場も含めて24時間一緒で。3か月くらい経ったとき、彼の360°すべての側面と喋り切ったという気がしました。そのとき、本当の意味で『同じ人間だ』と。『みんな、そんなに変わらない』と確信できたのがとてもいい経験でした」

バックグラウンドの違いによる怖さや劣等感はなくなり、誰に対してもディスカッションしていいんだ、という自信がついたといいます。
「意見の食い違いは“見ている事実の違い”であり、ロジックがそんなに乖離するわけじゃないと分かったんです。今では誰とでもあまり緊張せずに喋ることができます。大きな会社の社長さんでも特に緊張することはないですし、最後は友だちになることもあります」
“100点を目指すより、楽しく戦える80点のチームをつくる。”
エリック・シュミット氏にプレゼンした事業アイデアをもとに物部さんは起業します。2014年、皮膚科の遠隔診断治療支援サービスを立ち上げ、医師同士をオンラインでつなぎ診断サービスを行う「エクスメディオ」を設立しました。
「精神科医として、皮膚科症状をきれいに治すことは、精神科の患者さんにメリットがあると考えたのが始まりです。皮膚科疾患は精神科の症状を引き起こす原因となることも多くて、うまく治療できると睡眠薬を減らせるなどの可能性も大いにある。皮膚科専門医の診断をオンラインで受けられるようにしたかったんです」
当時はオンライン診断に対する逆風も強く、「診断がオンラインでできるはずがない」と批判を受けることもありましたが、丁寧な説明を重ね徐々に理解を得ていきました。「医療現場に専門医がオンラインで入り込めるスペースをつくった、先鞭をつけたのは自分たちだと思う」と振り返る物部さんですが、創業時から大切にしたのは“仲間とつくる企業”という考え方です。
「どうしても集中すると仕事の時間は長くなるので、楽しめる仲間と一緒にやりたい。解決したい課題があって、課題を解決するのはもちろん楽しい。それだけでは物足りなくて、課題解決のプロセスにおいても、友だちとワイワイしながらサークルのように解決したい。100点のチームよりも、楽しくて長く戦える80点のチームをつくりたいんです」
“高く飛ぶためには、しっかりとかがみこむこと。”
現在は高齢者の孤立・孤独の解決に取り組んでいる物部さん。きっかけは一人暮らしの父の変化でした。
「父の元気がなくなってきたと感じたので調べてみると、孤立・孤独による健康リスクの高さが分かったんです。死亡率が1.3倍に上がるという調査結果もあり、1.3倍というとヘビースモーカーと同程度です。タバコのリスクはみんな知っているのに、同じくらい深刻な孤立・孤独は十分な対策が取られていない。日本では31%のシニアが孤立・孤独であるというデータもあって、ここを解決したいと思いました」
60歳以上の9割超がスマートフォンを持つといわれる時代。オンラインで“広く、安く”解決できるツールを提供したいと考え、シニアのマッチングサービス事業を立ち上げます。

仲間とともに始めたこの事業を「少なくとも10年はやっていきたい」と語る物部さん。10年やり続けるには速いスピードで成長し続けることが必要で、成長するとまた新しい世界が見え、新しい視座がどんどん獲得できるといいます。
「新しいことを始めようとするときには、インプットの時間を長く取るようにしています。大きく飛ぶためにはかがみこむ必要があって、深くかがみこめばこむほど高く飛べると思っています。スタンフォードへの留学は起業に必要なインプットでしたし、今も週に1日、2日は意識してインプットの時間をつくっています。あとは、準備も大切です。プレゼンをするときは、何度も何度もつくり変え、原稿が体に染み込んで、自分の言葉で語れるようになるまで練習してから臨みます」
“人生を自分らしく切り開いていく。”
いくつもの事業を起業してきた物部さんですが、今は挑戦する人に対して優しい社会になってきているといいます。
「失敗しても次ができる社会になってきていると感じます。もちろんがむしゃらに頑張ることが前提で、リスクを取り、オーナーシップをもってやり切って、それでも社会の風が変わってうまくいかなかったときは、それなりに評価してもらえる世の中になってきています」
挑戦する人に優しい社会になってきているとはいえ、思いだけで踏み出すことには警鐘を鳴らします。学生時代に起業したタウン誌発行は一定の成果を得たけれど、ビジネスとして継続させるには足りないことが多かったと振り返ります。
「働くなかで直面した社会課題があったからこそ、医療系スタートアップのエクスメディオを立ち上げることができました。社会の仕組みや経済の流れを知ることは新たな挑戦に必要なことだと思います。加えて、“自分はこれができる”というものを働きながらしっかりとつくっていくこと。自分がなりたい、追いたい背中の人を見つけて、自分もできるようになっていくことが大切です」

なりたい人との差分を見つめ、自分に足りないものを認識することの重要性を強調する一方で、「人と比較することは全くしない」とも。
「SNSは見ないんです。人と自分を比較することは意味がないと思っています。高校生までは周囲との比較をしてたんですけど、負けたら悔しいし良くない感情が生まれる。比較しなくなってからは、誰かの成功を自分のことのように喜べるようになりました。SNSを見る時間をやりたいことにも使えるし、幸せな生き方が身についていると思います」
“人がどうしたら楽しく生きられるか”を追求し、仲間とともに新たな挑戦を続ける物部さん。人とのつながりを大切にする、挑戦する過程を楽しむ、やるからには準備を怠らず、全力を尽くす--。物部さんの大切にする生き方は、起業を志す人のみならず、目標に向かって挑戦するあらゆる人にとって、人生を切り開いていくためのヒントになるかもしれません。
(所属組織、役職名等は記事掲載当時のものです)

物部真一郎
超楽長寿株式会社 代表取締役
caravanは双日が発信しているメディアです。
https://www.sojitz.com/jp/about/