2026.01.22 UP
 元陸上選手の為末大さんは、人生の前半と後半を異なるテーマで生きています。
元陸上選手の為末大さんは、人生の前半と後半を異なるテーマで生きています。
現役時代は世界最速という目標を追い求めました。引退後は、あえて目的を追わない「遊び」の可能性を探求しています。
一見すると相反する生き方ですが、そこには変化の激しい時代をより良く生きるためのヒントが隠されています。
“走る哲学者”の言葉に耳を傾けました。
Text_Interview_Keigo Kawasaki
Photograph_Mina Suzuki
“世界一がいいことで、金メダルは素晴らしくて、タイムは0.1秒でも早い方がいい。
現役時代は明確な基準がある世界を生きていた。”
スプリント種目における日本人初のメダリストである為末さんは、1978年に広島県で生まれました。「子どものころはかけっこが好きな本の虫でした」と振り返ります。
競技を始めたのは8歳の時です。地元の陸上クラブで短距離種目に取り組むと、おもしろいようにタイムが伸びました。ジュニアオリンピックでは当時の日本記録を更新し、インターハイでも負け知らず。100mの選手としては挫折を経験しましたが、高校3年で400mハードルに転向すると、世界の頂が見えてきました。
「“世界最速になる”という目標から逆算して、今、何をすべきかの計画を立てる。自分のような体型であれば、どんな走り方をすればいいか、どこを鍛えればいいか。そんなことを考えるのが楽しくて、しょうがありませんでした」

現役時代の為末さんは、コーチをつけず、独自でトレーニングに励むスタイルで知られていました。読書と内省を繰り返しながら、自らの体と向き合う。その姿から“走る哲学者”とも呼ばれていました。
独自のスタイルが実を結んだのは2001年、カナダのエドモントンで開催された世界選手権でのことです。400mハードルに出場した為末さんは銅メダルを獲得。陸上のスプリント種目の世界大会で日本選手が表彰台に立つのは、これが初めてのことでした。決勝での47秒89というタイムは、四半世紀を経た今も日本記録として保持されています。

現役時代の為末さん(2001年9月、写真:毎日新聞社)
“目的がはっきりしている「次のレース」を探したかった。”
為末さんは3度のオリンピック出場と2つの銅メダルという実績を残し、2012年に競技を引退します。その後は陸上界を離れ、異分野へと飛び込みました。
ベストセラーとなった『諦める力』をはじめとする著書の執筆、アスリートの社会的自立を支援する活動や、スポーツに関わるスタートアップの支援にも取り組んできました。
2016年の全天候型ランニングスタジアムのオープンに当たっては館長を務め、大きな注目を集めます。さらに2021年の東京オリンピックでは、アスリートの経験や知覚を言語化する能力を生かし、さまざまな媒体でメッセージを発信しました。
傍目には華やかに見えるセカンドキャリアでしたが、自身では“違和”を感じていたと言います。

「引退後も現役時代のように、明確なKPIや目的を設定し、それを追求しようとしました。ただ、今ひとつ燃え切ることができませんでした。今振り返ると、自分自身の中で何をやりたいのかがわからないまま、放浪した10年だったようにも思います」
それは目的を追い求めた“人生前半のテーマ”の終わりでした。
“自分の思いの原点にあるものを深く掘り下げていくと、目的に向かう道が無数に見えてくる。
道は一つではないが、一つしか選べない。(著書『諦める力』より)”
為末さんの愛読書の一つに『ホモ・ルーデンス』という本があります。ドイツの歴史家ヨハン・ホイジンガの著作で、「遊び」についての哲学的な考察が記された一冊です。書名はラテン語で「遊ぶ人」を意味します。
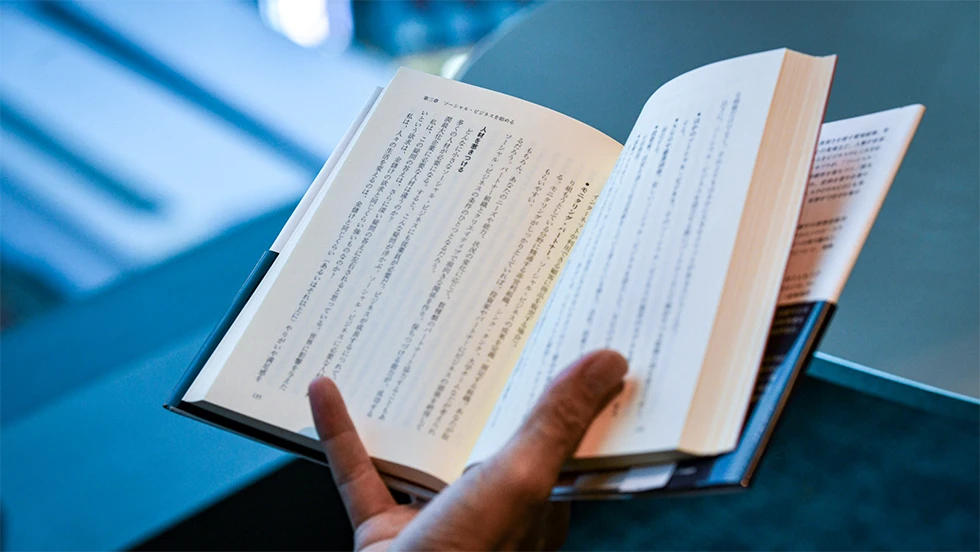
初めて読んだのは20代の半ばでした。当時は競技を続ける上でのインスピレーションを得たと言います。
「遊びとは、目的や意味から離れ、ただ“楽しいからする”行為のことです。目の前で起きていることに向き合い、感じながら、これって何だろう、このまま追いかけてみると何が起こるんだろうと“今、今、今”を繰り返していく世界です。
目線を先に置くのではなく、あえてずらして“今”に置く。そうすることで物事の新しい意味が見つけられたり、自分の想像の壁を越えたりするきっかけを与えてくれます」
振り返れば、為末さんの人生の転機にも「遊び」がありました。
100m選手としての挫折を味わった高校時代も、「400mハードルであれば世界最速になれるかもしれない」と視点をずらすことで再起しました。大学時代は、風変わりなトレーニングを手当たり次第に試したことでスランプを脱しました。競技から身を引いた後にキャリアをシフトできたのは、好奇心の赴くまま異分野に飛び込んでいったからです。
「遊びは世界を拓く力を持っている。その可能性を探究したい」
これが為末さんにとっての人生後半のテーマです。
“すばらしいものはいきなり全体なのだ。一つ一つを分析することなどできない。全体が、それそのままで素晴らしく、何一つ切り分けられないのが最高の状態である。(著書『熟達論』より)”
為末さんには忘れられない光景があります。2004年のアテネオリンピック選手村での出来事です。
「深夜の食堂でご飯を食べていたら、韓国の選手が『そのバナナを取って』と北朝鮮の選手に声をかけている場面に出くわしました。すると、声をかけられた選手は何事もなくバナナを手渡しました。普段は敵対するポーズを取らなければいけない関係なのに、何かのきっかけで、お互いを隔てる境界が曖昧になってしまった。そんな光景でした。
スポーツやオリンピックも『遊び』と同じようにお互いの緊張を解かし、越境し合いながら、包摂していくような力があるように思います」
為末さんが実行委員長を務める「大地の運動会」というイベントは、選手村での光景を再現する試みだと言えます。
新潟県十日町にある山間の集落で開催されるこのイベントは、国籍や地域、世代を超えて運動会を楽しむことを目的にしています。2025年は25カ国から約450人が参加し、ぱん食い競争や玉入れ、リレーに興じました。

大地の運動会であいさつをする為末さん(2024年、撮影:Nakamura Osamu)
「私たちは普段、人種とか性別とか、いろんな線であっちとこっちを分けますが、大地の運動会のようなイベントで、勝った、負けた、悔しい、なんてことをやっていると、だんだん、そういう境界がなくなってきます。わたしはこうした形で、社会に『遊び』を実装していきたいと考えています」
分断が進む時代において、「遊び」は世界を結び直す契機にもなりえるーー。為末さんの言葉からは、そんな希望を見い出すことができます。

“今、この瞬間に心が躍ることを大切にしてほしい。”
世界最速という目的を追い求めた前半生。迷いを経て「遊び」の可能性を探究し始めた後半生。
2つのテーマを生きる為末さんにとって、“より良き人生”とは何でしょうか。そんな問いを投げかけると、次のように答えてくれました。
「“固有の人生を生きることができるかどうか”ではないでしょうか。たいていの人は何らかのロールモデルを追いながら生きています。でも、長く生きていく中で、さまざまな想定外のことが起きてきます。それは失恋だったり、就活がうまくいかなかったりすることかもしれません。子どもの誕生や親の死と向き合うこともあるでしょう。
大事なのは、そうした固有の出来事をどう解釈して、どう自分の中にためていくかです。無駄に見えるかもしれませんが、長い人生で見ると、その積み重ねによって、自分にとっての固有の人生はこれなんじゃないか、という実感が生まれてくるように思います」
為末さんが言う固有の人生とは、“他の人では生きられない、自分だけの物語”のことです。
「今の時代は、ある目的に対して“最適”とされる情報を簡単に手に入れることができます。便利な半面、人が持つ可能性を狭めているようにも思います。目的と関係のないことを無駄だと排除していくと、固有性を生むサプライズは生まれませんし、世界も拡がりません。
自分の可能性を拓いてくれるモノは、常に自分の知らないところからやってきます。それを受け止めるには、“余白”や“ゆらぎ”といった『遊び』が必要なのだと思います」
為末さんはよく「目つきが変わった」と言われるそうです。
アスリート時代は抜き身のナイフのような鋭い眼光でした。それが今は、目に映るものをすべて慈しむような温かいまなざしをしています。
その変化は、為末さん自身が「遊び」によって自分の世界を拓き、固有の人生を生きていることの証です。
走る哲学者は言います。
「だから、今、この瞬間、心躍ることに飛び込んで」

(所属組織、役職名等は記事掲載当時のものです)

為末大
caravanは双日が発信しているメディアです。
https://www.sojitz.com/jp/about/